
共働きのご家庭が増えている今、保育園の存在は、仕事と子育てを両立するうえでとても心強い味方になっています。
「なぜ保育が必要なのか?」「どうやってその理由を書けばいいのか?」
保育園に申し込むときには、共働きだからといって自動的に入れるわけではなく、“なぜ必要なのか”をしっかり伝えることが大切です。
この記事では、共働き家庭が保育園を利用するうえで知っておきたいポイントや、よくある理由の例文、書類の準備方法などをやさしく解説しています。保育園選びや学童のこともあわせて紹介しているので、これから準備を始める方にもきっと役立つはずです。
保育を必要とする理由と共働き家庭の実情
共働き家庭にとって、保育園の利用は仕事と育児を両立するうえで欠かせません。特にフルタイム勤務やシフト勤務、育休明けの職場復帰などでは、保育が不可欠な状況です。在宅ワークであっても、業務に集中する時間が確保できず、保育の必要性が生じる家庭も少なくありません。
保育園を利用することはゴールではなく、送り迎えの調整や子どもの体調不良への対応、園との連絡など、日常的な工夫や負担も伴います。そのため、申請書では「保育がなぜ必要なのか」を具体的に伝えることがとても重要です。
保育園の選び方と入園の流れ
認可保育園と認可外保育園の違い
認可保育園は、国や自治体の基準を満たして運営されており、利用料も所得に応じて設定されます。一方、認可外保育園は独自基準で運営されており、柔軟な保育時間や少人数制などが特徴です。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、家庭のニーズに合った選択が求められます。
地域ごとの施設のメリット
自治体によっては、保育所や幼稚園との併設型、小規模保育、企業主導型など多様な選択肢があります。
通勤経路にある施設、きょうだいが通っている園、食育に力を入れている園など、家庭のライフスタイルと合うかを軸に比較検討しましょう。
入園申請時の注意事項
申請書の記入欄は、自治体や園によって文字数やスペースが限られていることがあります。限られたスペースに収めるには、ポイントを絞って簡潔に記載しましょう。一方、十分な記入欄がある場合には、家庭状況や勤務内容を具体的に書くことで、保育の必要性がより伝わりやすくなります。
また、勤務証明書や就労予定証明などの添付書類に不備がないように注意しましょう。希望園を第3希望まで記入する場合、すべての園について調査しておくと安心です。
入園希望理由の記載例と文例集
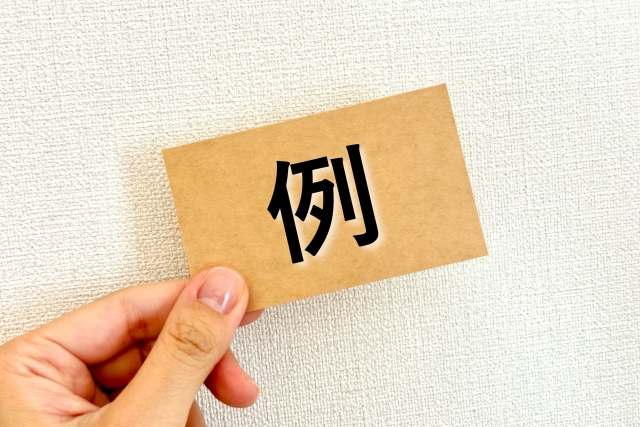
実際の申請書に記載する「入園希望理由」は、簡潔かつ具体的に記すことが大切です。以下に、共働き家庭でよく使われる入園希望理由の文例をいくつか紹介します。
短文例(記入欄が小さい場合に使える例)
※以下は申請書の記入欄が限られている場合に使える、簡潔な文例です。丁寧な言い回しで、主語と状況がわかるようにまとめています。
【例文1:フルタイム勤務の共働き家庭】 父母ともにフルタイム勤務のため、日中の育児が困難です。
【例文2:育休明けで復職予定】 母は育休明けで職場復帰を予定しており、日中の保育が必要です。
【例文3:在宅勤務だが業務に支障がある場合】 母は在宅勤務で、Web会議や納期対応が多く保育が必要です。
【例文4:夜勤やシフト勤務がある場合】 両親ともに不規則なシフト勤務のため、家庭での保育が難しい状況です。
【例文5:家庭状況により育児が困難な場合】 父はフルタイム勤務、母はパート勤務中で、近隣に育児協力者がいないため保育が必要です。
長文例(記入欄に余裕がある場合や詳細を伝えたい場合)
【例文1:フルタイム勤務の共働き家庭】 父母ともに平日9時から18時までのフルタイム勤務をしており、日中は家庭での保育が困難なため、保育園の利用を希望いたします。
【例文2:育休明けで復職予定】 母は現在育児休業中ですが、○年○月○日より職場復帰を予定しており、復帰後は就業時間中の保育が必要なため、入園を希望いたします。
【例文3:在宅勤務だが業務に支障がある場合】 母は在宅勤務ですが、電話対応や会議、納期対応などが多く、育児との両立が難しいため、保育園の利用が必要です。
【例文4:夜勤やシフト勤務がある場合】 父は日勤、母は病院勤務で夜勤やシフト勤務が不規則にあるため、家庭内での安定した保育が困難な状況です。そのため、保育園のご利用を希望しております。
【例文5:家庭状況により育児が困難な場合】 父はフルタイム勤務、母は現在パート勤務中ですが、祖父母など近隣に育児協力者がいないため、育児と仕事の両立が難しい状況です。家庭で十分な保育環境を整えることが困難なため、保育園の利用を希望します。
入園の合否と入園希望理由の関係

保育園の申し込みは先着順ではなく、ほとんどの自治体では「点数制(選考基準指数)」というルールで決まります。これは、保育がどれくらい必要かを客観的に判断するためのしくみです。
たとえば、両親ともにフルタイムで働いている家庭は点数が高くなり、在宅勤務やパートタイムなど条件によっては点数が低くなることもあります。
点数制で重視される主な項目
- 父母ともにフルタイム勤務(高得点)
- ひとり親世帯や要介護者との同居(加点対象)
- 在宅勤務や短時間勤務(条件によっては点数が下がることも)
- 書類に不備がないか(不備があると点数が付かないことも)
保育理由が合否に与える影響
共働きであっても、「なぜ保育が必要なのか」がうまく伝わっていなかったり、証明書が足りなかったりすると、希望の園に入れないこともあります。
特に在宅勤務や自営業の方は、どんな働き方をしていて、どうして育児との両立が難しいのかを、できるだけ具体的に書くことが大事です。
対策ポイント
- 自分の家庭状況が点数にどう影響するか、事前に自治体の選考基準を確認する
- 保育理由は簡潔に、かつ具体的に記載する
- 証明書類に不備がないよう、詳細は次のセクションで確認しながら早めに準備する
保育園申請に必要な書類と注意点

必要書類の準備と提出方法
・勤務証明書(雇用主発行、就業時間・勤務日数を明記) ・就労予定証明書(採用内定時に発行) ・保育の必要性を証明する理由書(所定フォーマットまたは自由記載)
これらの書類は、保育園の入園申請時に必ず提出が求められます。特に「保育を必要とする理由書」は、共働きであることを明確かつ具体的に記載することが大切です。
いずれも期限内の提出と正確な記載が求められるため、事前に自治体の案内をよく確認し、不備のないよう丁寧に準備しましょう。
補足:共働き家庭のための学童保育
学童保育の必要性と利点
小学校に上がったあと、放課後の子どもをどう過ごさせるか悩むご家庭はとても多いです。学童保育は、子どもが安心して過ごせる場所を提供しながら、自主性や社会性を育てる大切な場として役立っています。
放課後のサポートと子どもの成長
学童では、宿題を見てもらえたり、いろんな年齢の子と関わったりすることで、勉強だけでなく生活習慣も身につきやすくなります。
また、遊びや行事もあるので、リラックスした時間を過ごせるのも大きな魅力。おうちの人が帰ってくるまで、楽しく安心して過ごせる環境です。
学童保育の利用例と申し込み方法
学童には、公立の施設と民間の施設があります。申し込みの時期や条件は地域によって異なるため、早めに調べておくと安心です。
申し込むときは、働いていることを証明する書類や、利用理由を書いた書類が必要になることがあります。
希望園に入れなかったときの対処法

希望した保育園に入れなかった場合でも、落ち込まずに次の対策を講じることが重要です。以下のような選択肢があります。
二次募集を狙う
自治体によっては、入園辞退や転園により空きが出ることがあります。その場合、二次募集や追加募集が実施されることもあります。
認可外保育園を一時的に利用する
認可外保育園は利用料が高めですが、すぐに預けられる場合が多く、短期的な預け先として活用できます。
一時保育・家庭的保育の活用
家庭的保育(保育ママ)は、自治体に認可された保育者が自宅などで少人数の子どもを預かる制度です。0〜2歳児を対象に、手厚く家庭的な雰囲気で保育してもらえるのが特徴です。 一時的に地域の一時保育サービスや、家庭的保育(保育ママ)を活用しながら、次の募集を待つ方法もあります。
両親・祖父母の協力体制を整える
一時的に家族にサポートを依頼することで、乗り切ることができるケースもあります。
在宅勤務者向けの記載のコツ

在宅勤務でも保育園を希望する場合、「自宅にいる=育児ができる」とみなされることがあるため、申請時には保育の必要性を明確に伝えることが重要です。
よくあるNG例
- 「在宅勤務のため、保育園を利用したい」だけの記述 → 業務内容や時間帯の説明がなく、説得力に欠けます
記載のポイント
- 実際の勤務時間帯や作業環境を明記する(例:業務中はWeb会議や顧客対応が多く、育児と両立が困難)
- 納期やクライアント対応など、業務上の制約を具体的に示す
- 業務に集中できる環境が必要である旨を簡潔に伝える
例文: 「母は在宅勤務で業務時間は9:00〜17:30。Web会議・電話対応・資料作成などが多く、業務に集中する必要があるため、育児との両立が難しく、保育園の利用が必要です。」
共働き家庭の保育申請 よくある質問Q&A

Q. 「家や職場から近い」「園の方針が気に入った」などの入園希望理由は、選考に影響しますか?
A. 入園希望理由は、園の教育方針や立地への共感などを記載しても意味はありません。実際の合否は保育の必要性(就労状況や家庭事情)に基づく点数で決まります。そのため、選考においては「なぜ保育が必要か」を明確に記載することが重要です。
Q. 住宅ローン返済のため共働きでないと生活が厳しいのですが、それを理由にしても良いですか?
A. 経済的な理由は多くの家庭に共通しますが、保育園の入園審査では「経済状況」そのものではなく、「就労状況や勤務時間」などの客観的な保育の必要性が評価されます。そのため、住宅ローンや生活費の事情ではなく、父母ともに働いており日中に育児ができない状況であることを中心に記載することが重要です。
Q. 共働きでも入れないことはありますか?
A. はい、あります。保育の必要性が高い世帯から順に選考されるため、同じ共働きでも勤務形態や就労証明の有無で差が出ることがあります。
Q. 申請後に勤務条件が変わったらどうすればいい?
A. 変更があった場合は、速やかに自治体へ報告し、必要があれば書類を再提出しましょう。
Q. 書類に不備があったらどうなりますか?
A. 点数が付与されずに不利になる可能性があります。提出前に自治体窓口での確認をおすすめします。
Q. 第2・第3希望も真剣に考えるべきですか?
A. はい。第1希望が通らなかった場合に備えて、第2・第3希望も通わせたい園を選び、しっかり下調べしておきましょう。
まとめ
共働き家庭にとって保育は、子育てを支えるライフラインのひとつです。保育園選びや学童の利用、書類作成といった一連のプロセスは決して簡単ではありませんが、早めの準備と正確な情報収集が安心につながります。
今回紹介した「入園希望理由」の例文や、保育関連の基礎知識を活用して、自信を持って次のステップへ進んでください。子どもの成長を支える環境づくりは、家庭と保育の連携によってより豊かなものになります。

