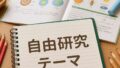テーマが決まらないときの考え方とヒント集。
「自由研究、そろそろ始めないと…」
そう思っても、なかなかテーマが決まらないというお子さんは多いですよね。
実は、テーマが思いつかないのは
“やる気がないから”ではなく、
選択肢が多すぎて迷っているだけなんです。
身近なことでも立派なテーマになりますし、
ちょっとした視点を変えるだけで「あ、これならできそう!」というアイデアが見つかるもの。
この記事では、
-
テーマが決まらない理由とその解決法
-
家でできる・簡単なテーマの見つけ方
-
親子で一緒に考えるコツ
を、やさしくわかりやすく紹介します。
夏休みの自由研究を、「焦り」ではなく「発見の時間」に変えていきましょう。
自由研究テーマが決まらない理由とその解決法

「自由研究、何をやったらいいのか分からない…」
そう感じるのは、とても自然なことです。
実は、テーマが決まらない理由にはいくつかのパターンがあります。
自分にどれが当てはまりそうか、いっしょに見てみましょう。
興味が見つからないときは「身近なもの」に目を向けよう
「興味のあることを書きなさい」と言われても、
いざ考えると「特にないかも…」と思ってしまうこと、ありますよね。
そんなときは、“毎日使っているもの”や“よく見ていること”から探してみましょう。
たとえば、こんなテーマも立派な自由研究になります。
-
冷蔵庫の中の食べ物はどれが早く傷む?
-
洗濯物は日なたと日かげで乾く速さがちがう?
-
家の中でいちばん音が出る場所はどこ?
「ふだんの生活 × ちょっとした疑問」だけで、すぐテーマが見つかります。
テーマが多すぎて選べないときは「条件」でしぼる
逆に、「やりたいことが多すぎて選べない」という人もいます。
そんなときは、次の3つの条件で考えてみましょう。
-
家でできること(外に出なくてもできる?)
-
お金がかからないこと(家にあるものでできる?)
-
時間がかかりすぎないこと(1〜2日で終わる?)
この3つをチェックして残ったものが、“今できるテーマ”です。
人とかぶりたくないときは「自分らしさ」を足す
「ほかの人と同じテーマはイヤだな」と感じるときは、テーマそのものを変えなくてもOK。
たとえば――
-
「ペットボトルロケットの作り方」→「ペットボトルの種類で飛び方は変わる?」
-
「朝顔の観察」→「花が開く時間を毎日記録してみる」
というように、
“自分で工夫した部分”をテーマにすれば、
それだけでオリジナル研究になります。
時間がなくて焦っているときは「短時間テーマ」を選ぼう
夏休みの終わりごろに
「もう時間がない!」というときは、
観察や調べ学習など、1日で終わるものを選ぶのがおすすめです。
たとえば、
-
氷を入れた飲み物はどれがいちばん長く冷たい?
-
近くのスーパーでいちばん多く売っているジュースの種類を調べる
-
家の中の観葉植物を写真に撮って比べる
短時間でも、まとめ方を工夫すれば立派な研究になります。
どんな理由でテーマが決まらない場合でも、
「できることから始めてみる」ことで必ず道が開けます。
つぎは、テーマを見つけるための考え方とコツを見ていきましょう。
自由研究テーマの選び方の基本
テーマを決めるときに大切なのは、むずかしいことを考えすぎないことです。
「どれが正解なんだろう」と迷ってしまうより、
「これならできそう!」と思えるテーマを選ぶほうが、最後まで楽しく続けられます。
ここでは、テーマ選びで失敗しないための3つの基本を紹介します。
① 「興味・身近・実現可能」の3つをそろえる
自由研究のテーマは、この3つを意識するだけでグッと決めやすくなります。
| 観点 | 考え方の例 |
|---|---|
| 興味 | 自分が「気になる」「見てみたい」と思えること |
| 身近 | 家・学校・公園など、すぐ調べられること |
| 実現可能 | 時間・材料・環境的にできること |
たとえば、
「氷の溶け方を比べてみたい」→家に氷とコップがあればできる。
これで3つの条件がすべてそろいます。
② 家でできるかどうかを最初にチェック
自由研究をスムーズに進めるには、場所と道具の確認も大事です。
「家でできるテーマ」を選べば、準備や片づけの手間が少なくなります。
たとえば、
-
キッチンでできる実験(塩・水・油・温度など)
-
ベランダでできる観察(植物・天気・光の変化など)
-
リビングでできる調べ学習(本・インターネット)
おうちの中でも、できることはたくさんあります。
③ 材料・道具・時間をメモしておこう
やってみたいテーマが決まったら、必要なものと日数をメモしてみましょう。
これを最初に書いておくと、実際に始めるときにあわてません。
たとえば、
-
材料:コップ・氷・塩・温度計
-
実験時間:1時間
-
観察回数:3回
このくらいの簡単なメモでも十分です。
あとでノートや模造紙にまとめるときも、研究の記録として役立ちます。
自由研究のテーマは、「難しいことを探す」よりも
“自分でもできそう”と思えることを選ぶのがいちばんのコツ。
次は、実際にテーマを探すときに役立つ
「迷ったときの見つけ方」を紹介します。
迷ったときのテーマの見つけ方

「どんなテーマにしたらいいか、やっぱり浮かばない…」
そんなときは、いくつかの“見つけ方のコツ”を試してみましょう。
ポイントは、「探す」よりも「気づく」こと。
身近な中にある「ちょっとした疑問」が、すでに自由研究のタネなんです。
① 「なぜ?」と思った瞬間をメモしてみよう
生活の中で「なんでだろう?」
と思うことを見つけたら、
ノートやメモ帳に書き留めておきましょう。
たとえば――
-
なんでアイスはすぐ溶けるの?
-
なぜ朝顔は朝だけ咲くの?
-
どうして金魚は口をパクパクしているの?
これだけで、もう立派な研究テーマの候補です。
疑問メモを3つ書くだけでも、自由研究の方向性が見えてきます。
② 家にあるものでできる実験を探す
テーマが思いつかないときは、「家にあるもので何ができるか」を考えてみましょう。
冷蔵庫・台所・リビングなど、身の回りを見渡すと、
自由研究に使える材料がたくさんあります。
たとえば、
-
キッチン:氷・塩・油・温度計(溶け方のちがい)
-
洗面所:石けん・水の温度(泡立ちの変化)
-
ベランダ:植物・土・天気(観察日記)
「買わなくてもできるテーマ」は、気軽に始めやすいです。
③ 去年の自由研究や友だちの作品を参考にする
自分の発想だけでは難しいときは、去年の作品を見返してみるのもおすすめです。
学校で掲示されていたり、
インターネットで紹介されている作品から、
「こういうテーマもあるんだ!」という気づきが得られます。
ただし、そのままマネするのではなく、
「自分ならここを変えてみたい」と思う部分を見つけてみましょう。
④ 親子で“会話しながら決める”のも効果的
親が「○○に興味ある?」と聞いてみるだけで、
子どもが自分の中の「気になること」に気づくことも多いです。
たとえば――
親:「最近、気になってることある?」
子:「うーん…スイカのタネってどうして黒いの?」
親:「それ面白いね!それを調べてみるのもいいかも」
こうした会話の中から、子ども主体のテーマが自然に生まれます。
テーマは“思いつくもの”ではなく、日常の中で気づくもの。
焦らず、気になったことを一つずつ拾っていけば大丈夫です。
次は、学年別におすすめできるテーマの例を紹介していきましょう。
学年別おすすめ自由研究テーマ
自由研究のテーマは、学年によって合う内容やレベルが少しずつ違います。
低学年は「身近でわかりやすいテーマ」、高学年になるほど「考察や工夫のあるテーマ」を選ぶのがおすすめです。
ここでは、小学生の学年ごとに分けて、すぐ取り組めるテーマを紹介します。
低学年(1〜2年生)におすすめのテーマ
まだ文字や文章を書くのが苦手な時期なので、
観察・比べる・作ってみるの3つがポイントです。
たとえば――
-
氷・砂糖・塩の中で、どれが一番早く溶ける?
-
雨の日と晴れの日で、葉っぱの色はちがう?
-
ペットボトルで風車を作ってみよう
-
色水を混ぜると何色になる?
→ 結果を絵や写真でまとめると楽しく続けられます。
中学年(3〜4年生)におすすめのテーマ
少しずつ文章で説明できるようになってくるので、
実験+記録+まとめのバランスを意識しましょう。
たとえば――
-
冷たい水と温かい水、どちらに砂糖は早く溶ける?
-
同じ植物を日なたと日かげに置くとどうなる?
-
家の中で一番明るい場所はどこ?
-
洗剤の量で泡立ちはどう変わる?
→ 1〜2日で結果が出るテーマが多いので、計画が立てやすいです。
高学年(5〜6年生)におすすめのテーマ
内容を自分で考えて進められるようになるので、
仮説を立てて検証する研究型のテーマに挑戦してみましょう。
たとえば――
-
ペットボトルの形でロケットの飛び方は変わる?
-
音の高さと空気の量にはどんな関係がある?
-
水に浮く・沈むの違いを調べてみよう
-
アルミホイルで作った船にどれくらい重りを乗せられる?
→ 途中経過をグラフや表でまとめると説得力アップ。
中学生向けのテーマ(応用編)
中学生になると、より科学的な思考やデータ分析ができるようになります。
難しい実験をする必要はありませんが、「理由を考える力」を意識して選びましょう。
たとえば――
-
飲み物の糖度を比べてみよう
-
食塩水の濃度と電気の通りやすさを調べる
-
植物の光合成の条件を変えて観察する
-
洗剤や漂白剤の環境への影響を考える
→ 調査結果をグラフ+考察でまとめる練習になります。
学年ごとのテーマを参考にしながら、
「これならできそう!」と思えるものを1つ選ぶことが大切です。
次は、テーマが決まったあとにどう進めるか、
研究の始め方とまとめ方の流れを見ていきましょう。
自由研究を進めるための具体的な手順
テーマが決まったら、次は実際に研究を進めていきましょう。
自由研究には、大きく分けて5つのステップがあります。
どの学年でも基本の流れは同じなので、親子でいっしょに計画を立てながら進めてみてください。
① 目的をはっきりさせる
まず、「なにを知りたいのか」を明確にしておきましょう。
たとえば、テーマが「氷の溶け方」なら、
→「どんな条件で一番早く溶けるのかを知りたい」
このように目的を決めておくと、実験や観察の方向がブレません。
② 予想を立ててみる
実験をする前に、「こうなるかもしれない」という自分なりの予想(仮説)を書いておきましょう。
たとえば、
→「温かい水のほうが氷は早く溶けると思う」
結果が合っていたかどうかよりも、
「自分で考えたことを確かめる」ことが大事です。
③ 実験・観察をする
いよいよ実験や観察のスタートです。
ここでのポイントは、
-
同じ条件で比べる
-
時間や回数を記録する
-
写真やメモを残す
という3つ。
結果をあとでまとめやすくするためにも、データを残す意識を持ちましょう。
④ 結果をまとめる
観察や実験の記録をもとに、結果を整理します。
グラフや表、写真を使うととても見やすくなります。
低学年は絵やシールでもOK。
高学年は、数値をグラフ化したり、結果を比較したりしてみましょう。
⑤ わかったこと・感想を書く
最後に、「やってみてわかったこと」や「気づいたこと」をまとめます。
たとえば、
→「氷は塩をかけると早く溶けることがわかった」
→「予想と違ったけど、理由を考えるのが楽しかった」
感じたことを自分の言葉で書くと、読んだ人に伝わる自由研究になります。
この5つの流れを押さえておけば、
どんなテーマでもスムーズに研究を進められます。
次は、親御さんが手伝うときのポイントとして、
「親の関わり方・サポートのコツ」を紹介します。
自由研究を手伝うときのコツ

自由研究は、子どもが「自分で考える力」を育てる良いチャンスです。
でも、実際には「どこまで手伝っていいの?」と迷う親御さんも多いですよね。
ここでは、親が上手にサポートするための3つのポイントを紹介します。
① 「代わりにやる」より「考えるきっかけを作る」
つい手を出したくなるときもありますが、
自由研究の主役はあくまで子ども本人。
親が先に答えを言うよりも、“考えるヒント”を出すサポートが効果的です。
たとえば――
「どんなことが気になる?」
「もし○○を変えたら、どうなると思う?」
こんな質問を投げかけるだけでも、子どもの思考が動き出します。
② 途中経過をほめる
自由研究は、結果よりも過程が大切です。
「自分でここまでできたね」
「昨日よりも詳しく書けてるね」
といった声かけで、子どものやる気はぐんと上がります。
特に高学年になるほど、結果にこだわって落ち込むこともあるので、
「途中を認めてあげる」ことが心の支えになります。
③ 一緒に記録や整理を手伝う
まとめの段階では、親が記録の整理や見やすさの工夫を手伝うとスムーズです。
たとえば、
-
グラフや写真の貼り方を一緒に考える
-
書く順番を決めるサポートをする
-
見出しや題名を一緒に決めてあげる
内容は本人に任せつつ、形を整える部分でフォローすると、完成度が高まります。
自由研究は、「結果を出す課題」ではなく、
親子で学ぶ“発見の時間”です。
テーマを決めて、考えて、まとめる――
その過程すべてが、子どもにとって大切な経験になります。
まとめ
自由研究のテーマは、最初から完璧に決めなくても大丈夫。
「気になる」「やってみたい」という気持ちが出発点です。
この記事で紹介したように、
-
決まらない理由を知る
-
身近なものからヒントを見つける
-
学年に合ったテーマを選ぶ
-
目的を持って進める
-
親があたたかくサポートする
この流れを意識するだけで、自由研究はぐっとスムーズになります。
大切なのは、「やらなきゃ」ではなく「やってみよう」という気持ち。
少しの工夫で、いつもの夏休みが“発見の時間”に変わります。
親子でいっしょに考え、作り上げた自由研究は、
きっと思い出にも残る素敵な作品になりますよ。
🪶 関連記事もチェック!
-
➡️ [自由研究ノートのまとめ方]
-
➡️ [自由研究の模造紙レイアウト]
- ➡️ [自由研究の模造紙書き方]