
義実家に年賀状を出すかどうかって、毎年なんとなく迷ってしまいますよね。
「義実家からもう来なくなったし、こちらももう出さなくていいのかな…」
「やめたい気持ちはあるけど、失礼にならないか心配」
「角を立てずにフェードアウトできる方法はないかな?」
こんなふうに、気持ちのどこかでモヤモヤしている方は意外と多いんです。
年賀状は家庭によって習慣が全然違うので、
“正しい答え” がひとつに決まっているわけではありません。
そのぶん、どうするのが一番いいのか判断しにくいんですよね。
この記事では、
-
義実家から来ないときに出さなくてもいいのか
-
出さないと失礼にあたるケースと、そうでないケース
-
自然にやめるための方法
-
角が立たない伝え方や例文
など、あなたが迷っているポイントをひとつずつ、やさしく解説していきます。
義実家との関係を大切にしながら、
あなたの気持ちも大事にできる“ちょうどいい距離感”を、一緒に見つけていきましょう。
義実家から年賀状が来ない…こちらも出さないのはアリ?

義実家から年賀状が届かなくなると、
「もううちも出さなくていいのかな?」
と考えるのはごく自然なことです。
実際、家族間の年賀状は“絶対に出すべき”という決まりはありません。
特に義実家の場合、年齢や地域、生活スタイルの違いもあって、年賀状の扱いは家庭ごとに大きく差があります。
たとえば、
-
義両親が年賀状じまいをした
-
高齢になり、年賀状を書くのが負担になっている
-
SNSやLINEでの挨拶に切り替えている
-
そもそも年賀状文化にこだわりがない
こんなケースも珍しくありません。
つまり、
義実家から年賀状が来ない=あなたが出さなくても失礼には当たらないことが多い
ということです。
とはいえ、長年の習慣や「失礼に思われたらどうしよう」という不安から、はっきり判断できない…という方も多いはず。
次の章では、
「どんな場合なら出さなくても大丈夫?」
「逆に、出したほうがいいのはどんなケース?」
といった“判断基準”について、わかりやすくお伝えしていきます。
義実家に年賀状を出さないのは失礼?判断基準はこの3つ
「出さないのは失礼になるのかな…?」
年賀状は“新年のごあいさつ”というイメージが強いので、どうしても気になりますよね。
でも実は、
義実家との関係性や普段のやり取りをふまえると、
出さないのが失礼にあたらないケースもたくさんあります。
ここでは、判断の目安になるポイントを3つにしぼって紹介します。
① 普段どれくらい交流があるか
日頃の関係が「年賀状よりも大事」です。
-
ほとんど連絡を取っていない
-
年に1回会うかどうか
-
義実家側も特に気にしていない
こういった場合は、
出さなくても関係が悪くなる可能性は低め。
逆に、頻繁に連絡を取っている・会っている場合は、
ちょっとした年始の挨拶があると“安心感”を持たれやすいこともあります。
② 義両親の価値観(年賀状にこだわるタイプか)
年賀状に対する感覚は、義両親の性格で大きく変わります。
例えば、
-
郵便物・形式を大切にするタイプ
-
「昔からの習慣」を重んじるタイプ
-
孫の写真を楽しみにしている義母
こういったタイプは、突然やめると驚く可能性があります。
一方、
-
あっさりしている
-
LINEや電話だけで十分という考え
-
そもそも年賀状を書かない
こんな義両親なら、出さなくても問題になりにくいです。
③ 目上扱いになるかどうか
義実家は「夫の両親」という立場なので、
一応“目上”にあたる関係と考えられます。
ただ、
これはあくまで一般的なマナー上の考え方であって、
絶対に出さなきゃいけないという決まりではありません。
“目上だから出さないと失礼”というよりも、
-
普段のやり取り
-
価値観
-
関係性
この3つで判断するほうが、実際はうまくいきます。
出さないことで角が立つケース・立たないケース
年賀状を出さないと決めても、
「義実家にどう思われるかな…」
と心配になってしまいますよね。
ただ、実際には“角が立つケース”と
“特に問題にならないケース”があり、
そこを理解しておくだけで判断しやすくなります。
角が立たないケース
◎義実家がそもそも年賀状を送ってこない
もっとも自然なパターンです。
相手が送らない=年賀状文化にこだわっていない可能性が高いので、こちらも気にせずやめてOKです。
◎普段からあっさりした関係
-
連絡は必要なときだけ
-
会うのは年に数回以下
-
義母・義父がドライな性格
こんな家庭は、
年賀状を「義務」と捉えていないことが多いので、
出さなくても関係が変わらないケースがほとんどです。
◎義両親が年賀状じまいを宣言している
最近は高齢の方中心に「今年で終わりにします」と告げる家庭も増えています。
こういった場合は、こちらも合わせてフェードアウトして問題ありません。
角が立つ可能性があるケース
◎義母が「孫の写真」を楽しみにしているタイプ
「毎年、孫の写真が届くのが嬉しい」という義母もいます。
急に届かなくなると、
「どうしたのかな?」
と不安に思われることも。
ただし、この場合もLINEの写真付き挨拶に切り替えれば十分代替できます。
◎義実家が“年賀状文化”を大切にしている
-
きちんとした挨拶を重んじる
-
手紙・はがきのやり取りを大事にする
-
毎年きっちり送ってくる
こういった義両親の場合、
いきなりゼロにすると驚かせる可能性があります。
事前にひとこと伝えるだけで印象は全く違うので、
後ほど紹介する“やわらかい伝え方”が役立ちます。
もうやめたい…自然にフェードアウトする3つの方法
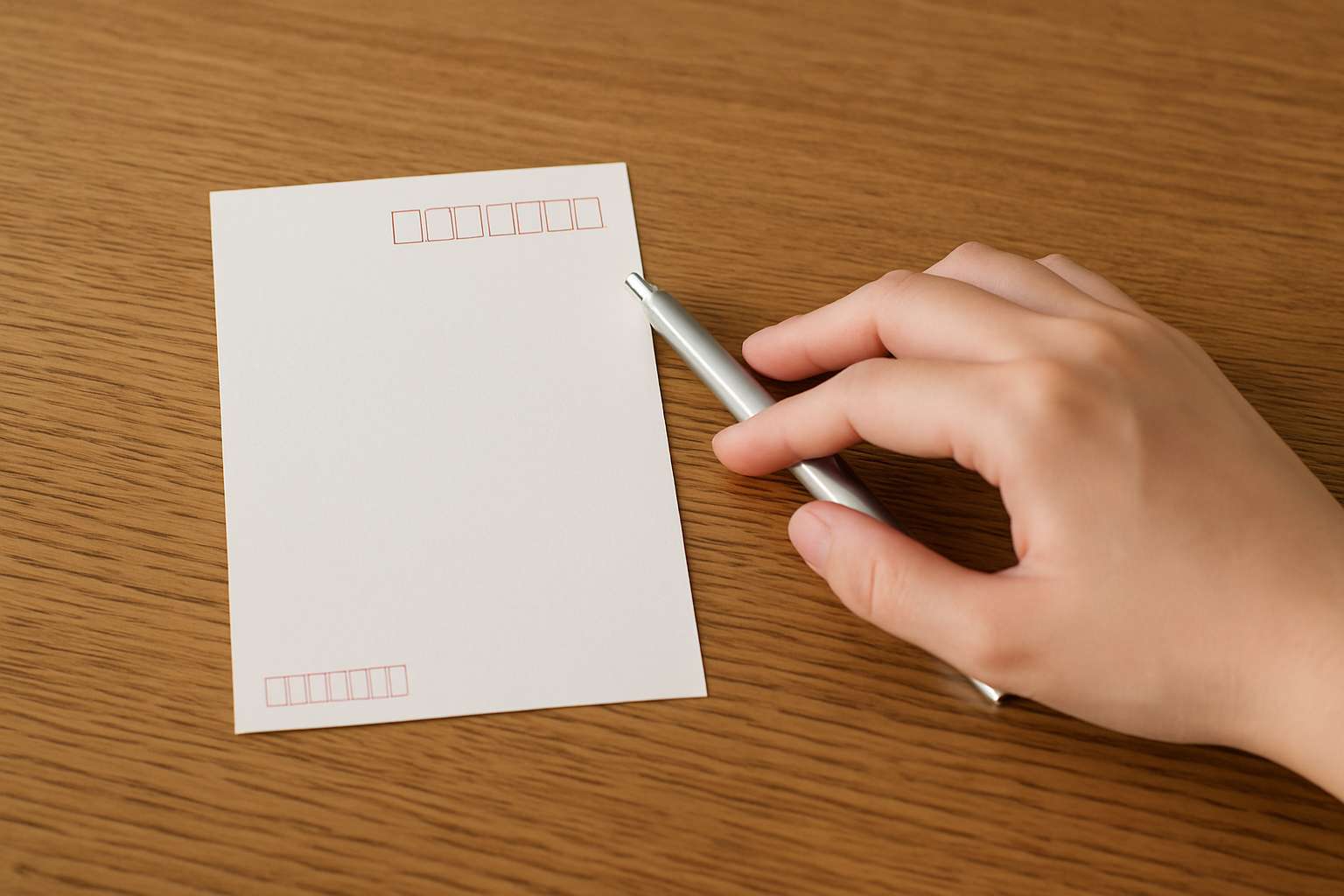
年賀状を続けるのが負担になってくると、
「そろそろやめたいな…」
という気持ちが出てきますよね。
でも義実家相手だと、
「やめるって言いにくい」
「怒られたらどうしよう」
という不安があるのも自然です。
ここでは、
角を立てずに自然にフェードアウトできる3つの方法を紹介します。
① 喪中をきっかけにやめる
義実家・自分たちどちらかが喪中になった年は、
年賀状をお休みする絶好のタイミングです。
喪中を経験したご家庭の場合、
「寒中見舞いのみ」に切り替えるのは自然な流れ。
そのまま翌年以降も年賀状を再開しなくても、
失礼には当たりません。
② LINEやメールで軽い新年の挨拶に切り替える
義実家が年賀状を送ってこなくなっている家庭では、
LINEでの挨拶に切り替えるだけで十分というケースが多いです。
たとえば新年に、
「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
また落ち着いたらお電話しますね。」
こんな軽い挨拶でも、義実家は意外と満足してくれます。
形式ばった年賀状より、
日常的な連絡のほうが今の時代に合っていると感じる義両親も増えています。
③ “年賀状じまい”をやわらかく伝える
最近は、60〜70代の方でも
「今年で年賀状は終わりにします」という
“年賀状じまい”を選ぶ人が増えています。
義実家に対しても、やさしい言い方で伝えれば大丈夫です。
例としては、
「今年から年賀状は控えようと思っています。
またLINEでごあいさつさせてくださいね。」
こんなふうに明るく伝えるだけで、
角が立つことはほとんどありません。
無理なく、自然に区切りをつけられます。
義実家に「今年から年賀状は控えます」と伝える例文

「やめたい気持ちはあるけれど、どう伝えれば角が立たないんだろう…?」
義実家への連絡は、どうしても気をつかいますよね。
でも安心してください。
やわらかい言い回しを使えば、すんなり受け取ってもらえることがほとんどです。
ここでは、状況別にそのまま使える例文を紹介します。
あなたの家庭のスタイルに合わせて、無理のない形を選んでくださいね。
夫から伝える場合の例文
夫から伝えるのが一番スムーズです。義両親も受け入れやすく、角が立ちにくいパターンです。
-
「今年から年賀状は控えるつもりだから、またLINEであいさつするね。」
-
「最近は年賀状を出す習慣がだいぶ減ってきたので、うちもそろそろやめようと思っています。」
-
「これからはメッセージで新年のあいさつをさせてもらうね。」
自分からLINEで伝える場合の例文
あなた自身から伝える場合も、丁寧な言い方であれば失礼にはあたりません。
-
「今年から年賀状は控えさせていただこうと思っています。今後はLINEであいさつさせてくださいね。」
-
「今年からは年賀状を控えて、メッセージでごあいさつさせていただく形にしようと思っています。」
-
「これからはLINEでごあいさつさせていただこうと思っています。」
やわらかく、「気持ちは変わらないですよ」というニュアンスが入ると安心感が伝わります。
義実家から来ないので、こちらも出さない場合の例文
もっとも自然なケースです。
義実家が年賀状を送ってこない場合は、「こちらもやめていいのかな?」と考えるご家庭が多いです。
軽い切り替えの挨拶だけで十分です。
-
「今後は年賀状を控えて、LINEでごあいさつする形にしようと思っています。」
-
「これからは年賀状はお休みして、LINEでごあいさつさせていただこうと思っています。」
-
「今年から年賀状は控えました。今後はLINEでごあいさつさせてくださいね。」
フェードアウト型のやわらかい文例
はっきり伝えるのが苦手な方はこちらがおすすめです。
-
「今年は年賀状を控えました。また改めてごあいさつさせてくださいね。」
-
「これからはLINEでごあいさつさせていただこうと思っています。」
-
「無理のない形でごあいさつさせていただきますね。」
義実家にだけ出さないのはアリ?
「実家には出すけど、義実家には出さないってアリなの?」
「片方だけやめるのは失礼になるのかな…」
こんな悩みを抱える方も多いのですが、
結論から言うと“義実家にだけ出さない”という選択は問題ありません。
年賀状は「家ごとの習慣」によって大きく変わるので、両家で揃えておく必要はないんです。
ここでは、迷わないための考え方をお伝えします。
それぞれの実家には“各家庭のルール”がある
あなたの実家は年賀状文化が根強くても、
義実家はLINEだけで十分と思っている…ということもあります。
つまり、
-
あなたの実家 → 年賀状を好む
-
義実家 → あっさりしていてこだわらない
というケースは普通にあります。
この場合、
それぞれの家庭に合わせた対応でOKです。
無理に両家で形式をそろえようとすると、
あなた自身の負担が大きくなってしまいます。
「義実家だけ出さない=失礼」ではない
義実家側が年賀状文化にこだわらないタイプなら、
こちらが控えても角が立つことはほとんどありません。
むしろ、
-
義実家が年賀状を送ってこない
-
LINEでのやり取りが増えている
-
年齢的に書くのが負担になっている
こういった状況なら、
こちらも無理せず合わせるほうが自然です。
迷う場合は“夫婦で話しておく”と安心
もし「本当に義実家には出さなくて大丈夫?」
と不安が残るなら、夫と一度だけ相談しておくと安心です。
夫がよく知っている義両親の性格から、
-
あの両親なら大丈夫
-
この言い方なら角が立たない
-
LINEだけで十分そう
といった判断がしやすくなります。
夫にひと声かけておくだけで、
「ちゃんと確認してある」という心の安心にもつながります。
義実家が喪中の場合・こちらが喪中の場合の対応
年賀状のやり取りをやめようか迷っている時に、
義実家や自分たちが“喪中”になることがあります。
喪中の年は、
そもそも年賀状を出さないのが一般的なので、
フェードアウトしたい人にとっては自然に切り替えられるタイミングです。
ここでは、喪中のときにどう対応すればいいかをわかりやすくまとめました。
喪中を理由に“やめる”のは自然
喪中の年は、年賀状の代わりに「寒中見舞い」を送るのが基本です。
義実家も喪中、自分たちも喪中、どちらの場合でも、
「今年は喪中のため年始のごあいさつは失礼させていただきます」
という扱いになるので、年賀状をやめる自然な流れが作れます。
そのまま翌年以降も年賀状を再開せず、
LINE挨拶だけに切り替えても不自然さはありません。
喪中のときに送る「寒中見舞い」の例文
義実家への寒中見舞いは、短くてOKです。
-
「喪中につき年頭のごあいさつをご遠慮させていただきました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。」
-
「喪中につき年賀状を控えさせていただきました。寒さ厳しい折、ご自愛ください。」
-
「喪中のため年始のごあいさつは失礼いたしました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。」
寒中見舞いを送ることで、
“こちら側の礼儀はきちんと守っている”という印象になります。
喪中の年にLINEで済ませるのはOK?
もちろん問題ありません。
最近は「寒中見舞い」も葉書ではなく、
LINEで伝えるご家庭が増えています。
たとえば、
「喪中のため年始のごあいさつは控えさせていただきました。本年もよろしくお願いします。」
これくらいで十分です。
義実家がLINE慣れしている場合は、
むしろ気軽に受け取ってくれます。
喪中明けの年にどうするか
次の年、年賀状を再開するか迷う方も多いのですが、
ここは あなたの家庭の方針で決めて大丈夫 です。
もし年賀状を本当にやめたいなら、
喪中明けのタイミングで再開しないのは自然な流れです。
-
LINEで挨拶だけにする
-
会う時に口頭で伝えるだけにする
どちらを選んでも失礼にはあたりません。
反対に、
「義母が丁寧なタイプだから再開した方がいいかも」と感じる場合は、
翌年だけ軽く出す、という方法もあります。
まとめ|無理に続ける必要はなし。あなたの家庭に合った距離感でOK
義実家の年賀状問題は、正解がひとつではありません。
義実家から送られてこない場合はもちろん、
関係性や価値観によっては こちらが出さない選択も十分アリ です。
大切なのは、
「義両親がどう思うか?」だけでなく、
あなたの家族にとって負担がなく、続けやすい形を選ぶこと。
-
義実家から年賀状が来ないなら、こちらも出さなくてOK
-
出さない選択が失礼にあたらないケースは多い
-
迷うときは夫と話しておくだけで安心
-
LINE・寒中見舞いで代替は十分
-
喪中はフェードアウトの自然なきっかけになる
年賀状はあくまで「挨拶の手段」のひとつです。
必ずしも毎年続けなければいけないものではありません。
あなたの家庭のペースに合ったやり方で、
気持ちよく新年を迎えられる関係を築ければ、それがいちばん自然です。

