
社会の自由研究って、ちょっと難しく感じませんか?
理科のように実験をしたり、
数字で結果を出したりするわけではないので、
「どうやってまとめたらいいの?」と迷う子も多いと思います。
でも、社会科の自由研究は「調べて、自分の考えをまとめる」ことがいちばん大切。
身のまわりのことや地域のことを見直すきっかけにもなります。
たとえば、地元のゴミ分別の仕組みを調べたり、
昔の町のようすを写真で比べてみたりするのも立派な研究です。
この記事では、
社会科の自由研究をうまくまとめるためのコツを、
ノートや模造紙の書き方、発表のポイントまで、わかりやすく紹介します。
「まとめるのが苦手…」という人でも大丈夫。
流れをつかめば、見やすく伝わる研究ノートが作れますよ。
社会科の自由研究は“考える力”をまとめる教科

理科とのちがいを知ろう
社会科の自由研究では、理科のように「実験して結果を出す」ことはあまりありません。
どちらかというと、調べたり、インタビューしたりして「なぜそうなっているのか」を考えることが中心です。
たとえば
「地域のゴミの分け方」
「昔と今の町のちがい」
「観光地の工夫」など、
自分の身近なテーマをもとに、“調査と考察”でまとめていくのが社会科のスタイル。
理科は「結果をもとに原因を探す」教科ですが、
社会科は「事実をもとに理由を考える」教科とも言えます。
だからこそ、自分の意見や感じたことを書くことが評価されやすいのです。
社会の自由研究で多いテーマ例
社会科の自由研究は、テーマの幅がとても広いのが特徴です。
興味のある分野を選ぶと、調べるのもまとめるのも楽しくなります。
たとえばこんなテーマがあります。
-
地域のごみ分別のしくみを調べてみよう
-
昔の商店街と今のショッピングモールを比べてみよう
-
災害への備えを調べて、自分の町の防災マップを作ってみよう
-
伝統行事やお祭りの意味を調べてみよう
-
観光地の取り組みや外国人観光客への工夫を調べてみよう
どのテーマも、「調べて→まとめて→考える」という流れで進められます。
理科のように実験道具がいらない分、身近な出来事をテーマにしやすいのが社会科の魅力です。
まとめる前に決めておく3つのポイント
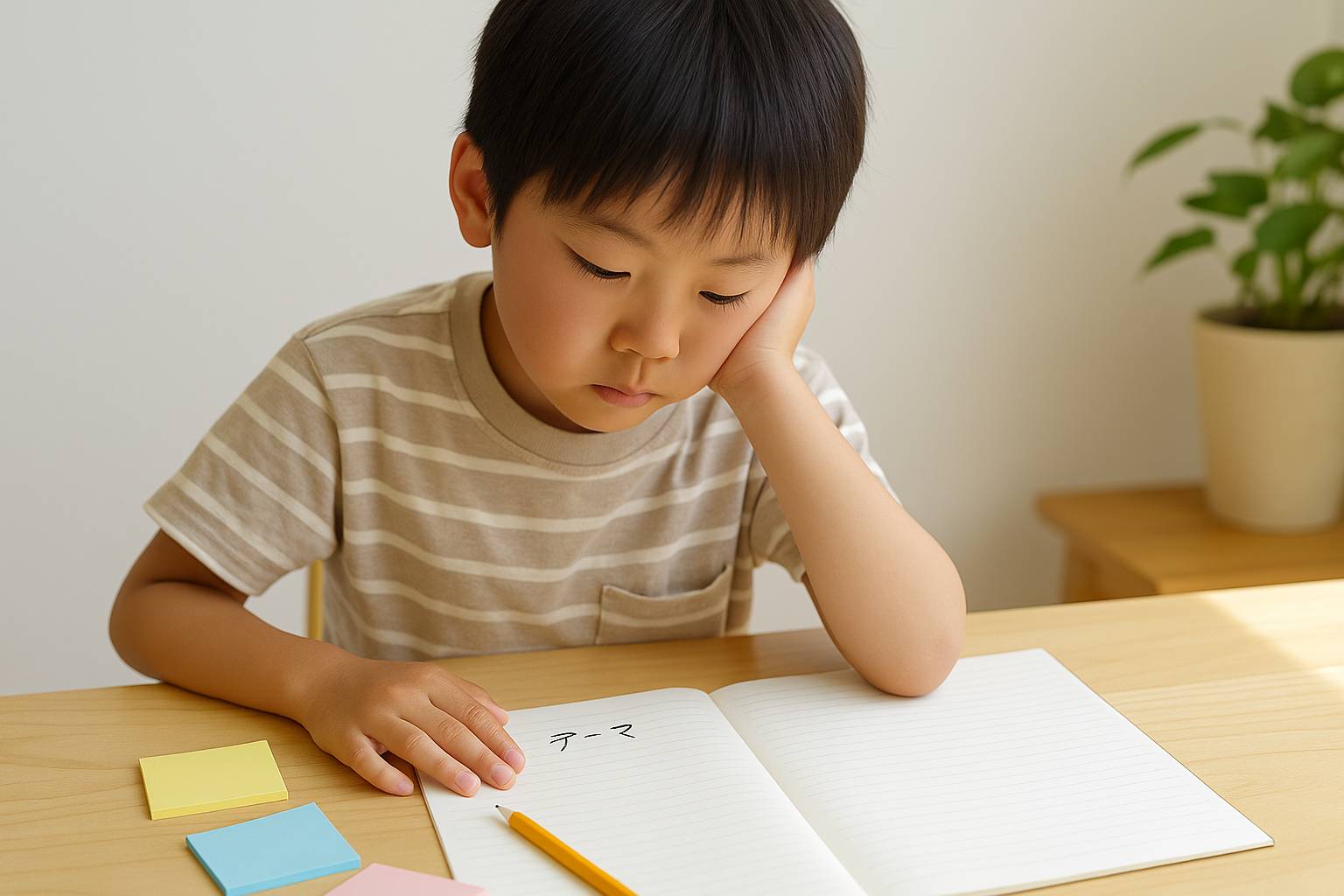
① テーマと調べたいことをはっきりさせる
社会の自由研究では、まず「どんなことを調べてみたいのか」を決めるのが第一歩です。
これがあいまいだと、調べる内容が広がりすぎて、まとめるときに困ってしまいます。
たとえば、
-
「なぜ地域によってゴミの分け方がちがうのか?」
-
「昔の商店街と今のショッピングモールはどう変わったのか?」
といったように、「○○について調べたい!」という気持ちがわかるテーマにしておくのがおすすめです。
最初に“調べたいこと”を一文で書いておくと、発表や模造紙にもそのまま使えます。
② 調べ方・情報の集め方を整理する
社会科の研究は、情報をどう集めるかで内容の深さが変わります。
図書館で資料を探すだけでなく、アンケートやインタビューを取り入れると、よりオリジナリティのある研究になります。
たとえば、地域の人やお店の方に話を聞いたり、学校でアンケートをとったりするのも立派な調査です。
大切なのは、「自分で調べた証拠(データ)」をしっかり残すこと。
メモや写真をとっておくと、まとめるときに役立ちます。
③ ノート・模造紙どちらでまとめるか決める
調べた内容をどんな形でまとめるかも、早めに決めておきましょう。
-
模造紙:発表や展示向け。写真やグラフを大きく貼るのに向いています。
-
ノート:提出用や記録向け。整理した順にまとめやすいのが特徴です。
自分がどんな発表をしたいかをイメージすると、どちらを選ぶか決めやすくなります。
模造紙とノート、どちらを選んでも「見やすく整理する」ことがいちばん大切です。
社会の自由研究|模造紙のまとめ方と構成例

模造紙の基本レイアウト
模造紙でまとめるときは、まず全体の「流れ」を意識することが大切です。
読む人が一目で内容を理解できるように、上から下、左から右へ自然に目が動くように並べましょう。
おすすめの配置は次の通りです。
-
上の段:テーマ・目的・調べたきっかけ
-
中央部分:調べたこと(地図・写真・グラフなど)
-
下の段:自分の考え・まとめ・感想
この順番で並べると、発表や展示でも見やすく、聞き手に伝わりやすい模造紙になります。
全体を最初に鉛筆で軽く下書きしておくと、バランスよく仕上げられます。
見やすくするための配置のコツ
-
文字は大きめに書き、見出しは太く目立つようにする
-
写真やグラフは中央あたりにまとめる
-
色ペンを使うときは、赤=タイトル、青=データ、黒=本文などに分ける
また、文章ばかりになると読みにくいので、
吹き出しや矢印を使ってポイントを補足するとぐっとわかりやすくなります。
「見やすさ=伝わりやすさ」という意識で作るのがコツです。
タイトルとまとめ欄の工夫
タイトルは「調べたこと+自分の視点」を入れると印象が良くなります。
たとえば、
-
「ごみの分け方はどうしてちがうの?」
-
「昔の町と今の町をくらべてみた」
など、少し“話しかけるような言い方”にすると親しみやすくなります。
下のまとめ欄では、
「調べてわかったこと」だけでなく、
「これからどうしたいか」「自分が考えたこと」を書くと、より深い内容になります。
ノートでまとめる場合のポイント
見開き1ページで「調べたこと」をわかりやすく整理
ノートでまとめるときは、模造紙よりもコンパクトに書く必要があります。
見開き1ページの中に「テーマ → 調べたこと → 自分の考え」を流れとしてまとめると、読みやすく仕上がります。
ポイントは、「何を調べたか」がすぐわかるようにすること。
見出しをつけたり、色ペンで大事な部分を囲んだりして、先生がパッと見て理解できるようにしましょう。
メモ・ふせん・図を使って整理する
調べた内容をそのまま清書しようとすると、うまくまとまらないことがあります。
まずはメモやふせんを使って、調べたことを分けて並べてみましょう。
「どんな順で書くとわかりやすいか?」を考えると、ノートの構成が決まりやすくなります。
表や簡単な図で整理するのもおすすめです。
社会科では、数字や場所などの情報を見える形にすると伝わりやすくなります。
清書の前に「章立て」を決めておくとスムーズ
いきなり書き始めるよりも、「1. テーマときっかけ」「2. 調べたこと」「3. わかったこと・まとめ」など、
小さな見出しをつけてから書くと、内容が整理されやすくなります。
見出しごとに少しスペースを空けて書くと、後から写真やグラフを貼るときもきれいに配置できます。
ノートでも“レイアウトを意識する”ことが、見やすく伝わるまとめ方のポイントです。
社会科らしい見せ方のコツ

グラフ・地図・写真を上手に使う
社会科の自由研究では、調べたことを“目で見てわかる形”にするのが大切です。
文章だけで説明するよりも、グラフや地図、写真などを使うとぐっと見やすくなります。
たとえば、アンケートをとったなら円グラフ、地域のようすを紹介するなら地図や写真を入れると効果的です。
社会科の研究は「事実を伝える教科」なので、視覚的にまとめることが説得力につながります。
文章を短く、箇条書きで要点をまとめる
社会科では、調べたことを“説明する力”が求められます。
ただ、長い文章で書くと読みにくくなるので、なるべく短く区切って書くのがコツです。
「〜だと思いました」「〜がわかりました」などの文を1行ごとにまとめたり、
箇条書きでポイントを整理したりすると、読みやすく整理された印象になります。
見出しや番号をつけると、模造紙でもノートでもスッキリ見えます。
発表時は「なぜ?」に答える意識で話す
社会の自由研究では、「調べたこと」だけでなく、
「なぜそう思ったのか」「どうすればよくなると思うか」を伝えると印象が強くなります。
発表のときには、
先生や友だちに質問される気持ちで、
「なぜそうなのか?」を自分の言葉で話せるようにしておきましょう。
調べたことに“自分の考え”を少し加えるだけで、研究の深さが一段と伝わります。
発表・提出の前にチェック!
誤字・グラフの単位・写真の貼り方を確認
せっかく時間をかけてまとめても、ちょっとしたミスがあると印象が下がってしまいます。
清書が終わったら、まずは文字や数字のまちがいがないかを確認しましょう。
特にグラフの単位や数字は要注意です。
「%」や「人」「回」などの単位をしっかり書いておくと、見る人にとってわかりやすくなります。
写真や図を貼るときは、まっすぐ貼れているか、説明文がついているかもチェック。
「どんな場面の写真か」がわかるように、一言コメントを添えておくと丁寧な印象になります。
友だちや家族に見てもらってわかりやすいか確認
自分では見やすくできたと思っても、他の人が見ると「少しわかりにくい」と感じることがあります。
完成した模造紙やノートは、家族や友だちに見てもらいましょう。
「どこを見ればいいかわかる?」
「タイトルと内容は合ってる?」など、
質問してもらうと改善点が見つかります。
見やすさの最終チェックとして、第三者の目で確認することが大切です。
タイトルと結論が合っているか最終チェック
最後にもう一度、タイトルとまとめの内容を読み直してみましょう。
「タイトルで調べたいと言っていたこと」に対して、
「まとめで答えが書けているか」を確認します。
もしズレていたら、タイトルを少し直すのもOKです。
タイトルと結論がぴったり合っていると、全体に一貫性が出て、完成度がぐっと上がります。
まとめ
社会科の自由研究は、「調べて考える力」を形にする教科です。
理科のように結果を出すことよりも、自分の考えをどう伝えるかが大切になります。
テーマを決めたら、目的をはっきりさせて、調べたことを見やすく整理しましょう。
模造紙ならレイアウトを意識して、ノートなら順序立てて書くと、誰が見てもわかりやすくなります。
また、発表や提出の前にもう一度全体を見直すことも大切です。
「タイトルと内容は合っている?」「数字や単位にまちがいはない?」といった最終チェックで、完成度が上がります。
社会の自由研究は、身近なことを深く考える良いチャンス。
ぜひ、自分の気づきや意見を自信をもってまとめてみてください。
他の教科も含めた全般的なまとめ方を知りたい方は、こちらもどうぞ。
👉 自由研究のまとめ方・書き方|模造紙・ノート・表紙まで解説
他の教科のまとめ方も知りたい方はこちら。
👉 親子でできる理科の自由研究|わかりやすいまとめ方と見せ方のコツ

